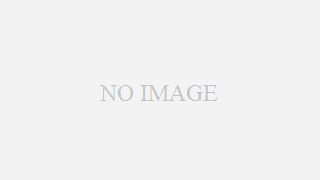 インフラ
インフラ オンプレミス
自分の家でご飯を作るイメージ。料理道具(サーバー)も厨房(データセンター)も全部自前。好きに改造できるけど、買い物や掃除も全部自分でしなきゃいけない。クラウド普及前はこれが当たり前だったんだ。
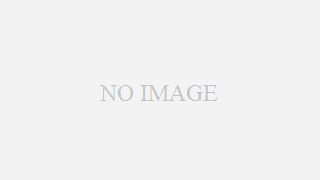 インフラ
インフラ 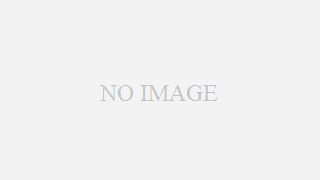 インフラ
インフラ 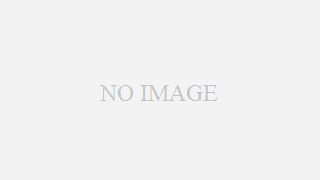 インフラ
インフラ 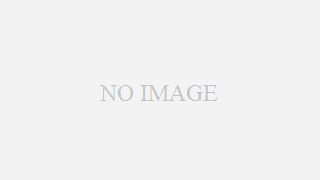 インフラ
インフラ 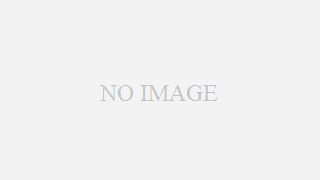 インフラ
インフラ 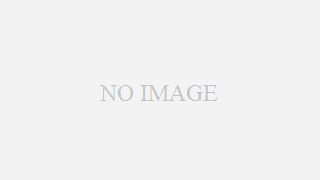 インフラ
インフラ 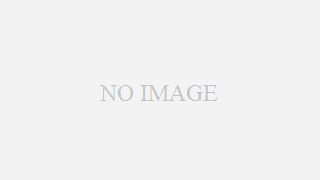 インフラ
インフラ 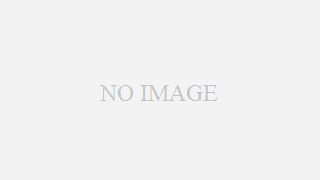 インフラ
インフラ 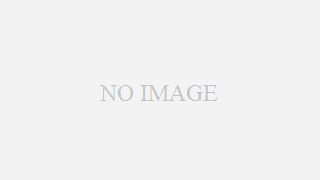 インフラ
インフラ 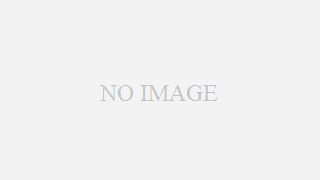 インフラ
インフラ